| �@�͂�邫�ʂ闷�������v�� |
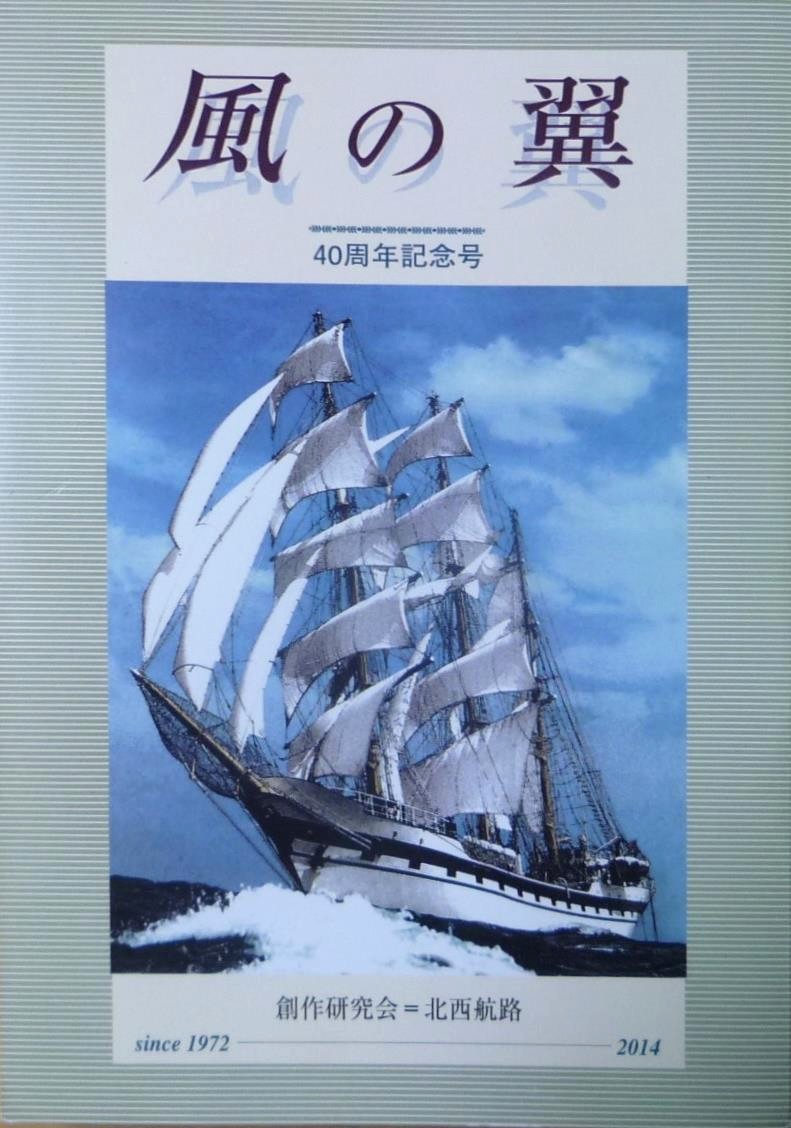
���炭�O�̂��Ƃ����A����r�m�r�ŁA���A���{�r�e�̃g�b�v�����i�[�ł��鏗����Ƃ̕����A���ꂱ��@��o�����̉����������Ɋւ���b���A�摜�t���ŃA�b�v���[�h���Ă����i����l���A���āu����}�v�ɂ����Ƃ��ŁA���̊W�̕i�X���N�W���Ă����Y�����������j�B
���̒��ɁA���ɂƂ��Ă����ɉ����������̂��������B��㔪��N�̃t�@���W���u�Ȋw���E�v�ł���B�ʊ��l�̂���́A���̕��͂����߂Ă��̎G���̃��^�[���[���ɍڂ������ŁA�摜�����āA���̍��̂��Ƃ��v���o�������ł��A���������ƁA�����Ԃ�̋C�p���������Ƃ����ݏグ�Ă���B
�Ȋw���E�Ƃ́A���̓��{�r�e��]�E�����[�h�I�t����F�F�V�����A�t�@���_������ɔ��s���Ă����t�@���W���ŁA�n��Ɣ�]�����Ƃ���d�h�̓��l���������B
���́A���̑O�̍��A��㔪��N�̎l�ꍆ���A�m���r�e�}�K�W���̃t�@���W���Љ�y�[�W�œǂ�ŁA�����ɍڂ��Ă���F���́u�r�e��]���@�_�����v�Ǝ���̃��o�[�g�E�X�R�[���Y�̂r�e�]�_��ǂ݂����āA���߂��̂����A�������ɂ́A��R���Q�V�����A�u���J���M�\�\�F�F�V���ցv�Ƃ��āu�r�e�ɂ����钴�z���݂̏����ɂ��āv�Ƃ������͂���e���Ă���A�����A���̕��ʂɂ��č�i���M��A���ꂱ��l�@���Ă������ɂ́A������ʔ����āA�G���̂�������˂āA�F���ɏ������������Ȃ��A���̍��̃��^�[���[���Ɍf�ڂ��ꂽ���悾�B
��R�����i���́A�������̃y���l�[�����A�܂�ő��d�l�i�҂̂悤�Ɏ����Ă����邪�A�ʓ|�Ȃ̂ŁA�ȉ��A�����Ăԁj�́A�F���������ŘA�ڂ��Ă������A�t�@���W����]�ɂ����āA�������Ŏ�ɂ��Ă���u���̗��v�����̍�i�ɑ��ĒF���������]�ɂ��āA����ΑR���_�̌`�ŁA���̏��������̔��_�����J���M�ő������炵���B�������������ɂ́A�Ȃ�̃o�[�^�[�����A���̍�i�u�N���X�^���b�V���E�Z�V���A�X���Z�v�܂ōڂ��Ă����i�����ɁA�F���̍Ĕᔻ���ł���u���J�ԐM�v���ڂ��Ă����̂����j�B
���́A�܂��A����A�ւ���Ƃ����u���̘_���̌��ɂȂ�����i��ǂ܂Ȃ��܂܁v�ŁA���̘_���Ɍ��y�����킯�����A������_�@�Ƃ��ē�R�����Ƃ����ʂ��n�܂�A���̍�i���ڂ����u���̗��v�̌b���������A�Ȍ�A�F�F�V�Ɠ�R�������Ƃ̕t���������n�܂����B
����͎��̂r�e�l���ɂ����Ă��A���ɑ傫�ȏo��ƂȂ������A���̌�F�͍��ɂ�����܂ő����Ă���B
���݂�ƁA�Ȋw���E�̎l�ɂ́A�F������̎莆���͂��܂�Ă���A����N�l����Z���t�̂���ɂ́A�܌��ɕ����Ɋw��ōs���̂ŁA����������|�A�L����Ă���B�����A���͓�����B�Ƃ͂����A���Ƃ̕������牓���������̒n�ɂ����̂����A���̋@����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ǝv���ċA�Ȃ��A���������F�������Ƃɔ��߂āA��x���܂łr�e�ɂ��Č�荇�������̂��B
���̂���l���玄�����e���͂ƂĂ��傫���A���̈Ӗ����炵�Ă��A���̍��́A������A���ɂƂ��Ă͎��ɗ��j�I�ȃt�@���W���̃C�V���[�Ȃ̂ł���B
�����A���͈�㎵��N�ɂr�e�}�K�W���̃R���e�X�g�œ��܂��A���̔N�̂����ɎO�قǍd��Ƃ�܂�����i�����������A�قڎ�܂Ɠ��������đ�w�𑲂��A�Љ�l�ƂȂ������́A�����̐l���̕��j�Ɏ�̌˘f���������A���̂܂ܓ̂�炶�őn��𑱂��Ă����̂��ǂ����A���̍��A�����������Ă����B
�O�쏑�������ƁA���N�قǓ��Ȃ̂��߂Ɏ��M���x�݁A����G���u�K���v�̑��ژ^���������A�}���K�ł́u��͐ԓ��Ձv��`�������Ď~�߂���A�܂��A�v����Ɍy���������������Ă����������͂��ށB
���̌�A�Z�Z���̒������r�e�}�K�W������āA�Y�������������j���āA��N�قǂ����āA�uTrial And Terror�i�ȉ��s���s�j�v�Ƃ����������E�g���c�L�[�Ȃ��l���́u�ŏI�́v�ɓ�����A���ʓI�ɘZ�Z�Z�����z���钷�҂������グ�āA�r�e�}�K�W���ɑ������̂����A����͂����Ȃ��v�ƂȂ����B�����Ɉ�̒������r�₦���B
���ꂪ���Z�N�Ă��甪��N�̓ɂ����Ă̂��ƂŁA�Ȋw���E���ŏ��ɋ��߂����́A�����ɂ͂��܂ꂽ�F���̎莆�̓��t���A����N������Z���Ƃ���̂ŁA�u�s���s�v�������I���āA�������A�r�e�}�K�W������͂��̕Ԏ����Ȃ��A�T�����Ă��������̂悤�Ɏv���i��ɏ㋞�����܂�A�����A���̒S�������������ҏW���ɉ���Ē��ɕ�������A�`���Ŏ��̂悤�Ȃ��̂��ڂ��Ă����̂ŁA����͂��t�U�P���Ǝv���A�Ō�܂œǂ�ł��Ȃ��A�Ƃ�������܂�Ȃ��b�������B���̌�A�ʓǂ������ʁA��͂�j�]����������Ƃ̗��R�ŁA�u�����v�ɖv�ƂȂ������߁A���l�N�ɂȂ��āA���̍��A�F���炪�Q�悵�Ă����u�r�e�̖{�v�ɖ����Œ������A�ŏI�͂̎�O�œ������p�����A���ǁA���ɕ��������D�ƂȂ����j�B
������ɂ���A���̍��̎��́A�����������������̂ƁA�R�}�[�V�����Y���̊ԂŁA�r���ɕ��Ă����悤�Ɏv���B
����ŁA���̍��A�������̂�������B�n���̃}���K���l���̋��߂Łu���H�v�Ƃ����A��ɏ��������āu�������v�Ȃ�A�쒷�҂̈ꕔ�ƂȂ�A���}�W���j�[�g�Ƃ������z�s�s�𒆊j�Ƃ��镨����}���K�ŕ`�����肵�Ă����B���Ȃ킿�A�������Ƃ��āA���ꂱ��Ǝ����̐��E�\�z�ɂ������Ă��������ł�����B
�����Ƃ��A���N���T�{���Ă���ƖO����̂��A���傤�ǂ��̍��A����N�̉č�����A���͂ӂ����ђ��f���Ă����u��͐ԓ��Ձv�������n�߁A��N���قǂ����āA����N�̏H�ɂ́A�ꉞ�̊����������B���Ȃ݂ɁA������܂���������i���Z�Z���̒��҂ƂȂ��Ă��܂����̂ł���j�Ƃ̗��R�ł�������ƂȂ����B�S���ҏW������A�債�������������Ȃ��A���s���ꂽ�̂́A���a�̌����I���߂��A�����N�ɂȂ��Ă��炾�����B
���̊ԁA���Ɠ����Ńf�r���[�����_�ђ������́A���͓I�ɂr�e�}�K�W���Ɋ�e���A����N�ɂ͑���i�W�u�ςƗx��v���㈲���A�V�V���[�Y�Ƃ��Ċ��s���n�܂������{�r�e�m���F���Y�ɂ��u���Ȃ��̍��Ɉ��炬����v���o���ȂǁA�ΏƓI�Ȋ���Ԃ肾�����B�ł��Ă����������Ȃ���ʂ����A�s�v�c�Ǝ��͏ő����A�����݂������Ȃ������B���̃V���[�Y�̃��C���i�b�v����R�ꂽ���Ƃ��܂߂āA�i�����ĕ]�������قǂ̎d�����ĂȂ�����A���R�����A�Ƃ����j���̐����ȑa�O���͂��������A�ł���i�݂��Ȃ������̂ł���B�����������Ă�����̂́A����قǑ��l�Ƃ́A���邢�͐��Ԃ̎��v�Ƃ͈قȂ��i�Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ��A���炽�߂čĊm�F���Ă����B���A�l����ƁA���̂悤�Ȃ��̂������Ǝv���B
����ɂ����A���́A��\�܍��߂������炢����A�܂�R���e�X�g�Ŏ�܂��A�Љ�ɏo�����傤�ǂ��̍�����A���l�Ƃ̋����A�Ƃ������A�N���Ɠ������ŁA�݂��ɋ��������ĉ������l������A�Ƃ������l���̃��[�X����~��邱�ƂɌ��߂Ă����B
���ł���Α�p���Y�����Ă�������A�����������ƂƂȂ��āA�����{�ŐH���Ă������M�͂Ȃ��������i�ƂĂ�����ȑ����_�o�͎����ɂ͂Ȃ��A�Ǝv���Ă����j�A�����炱���A�����������̂��������ƍl���Ă����B���l�̕]���͓�̎��������B�܂��A�����A�����̍앗�ł́A�}�C�i�[�����āA�ƂĂ��r�e��܂��l��悤�Ȕėp���̍�����i��������������Ƃ��v���Ȃ������Ƃ������Ƃ͂���B
�܂��A��w�̐E���Ƃ��Ă��A���g�h�B�Ȃǔ��o���ᒆ�ɂȂ������B
���Ԋ�Ƃ���āA���Ƃ��Ƃ��A�E�����ɗ����A�悤�₭�����荞���ƌ����������E�i�����j�ŕ����ȁA�������̉ʂĂȂ鍑����w�ɓ��Ȃ������́A��������w�}���قƂ��������B�̂Ȃ��ŁA�o�����悤�ȂǁA�l�������Ȃ������̂��B
�ǂ����݂��`�������̒��ł͍ʼn��w�ɑ����镶���ȁi���E���ȏȁj�́A���[�g�D�ł��鍑����w�ł́A���̒��ň�ԏ�ɍs�����Ƃ���ő�w���̔ԊO�n�I�ȑg�D�ł���}���ق̎����������g�b�v������A�����ւ̍��������ȂǂƂ͖����̐��E�ŁA�o�J�o�J�����Ǝv���Ă����̂��B�ǂ����A�����̑�w�}���ق́A�R���s���[�^���������x��i�ʏ́E�I�t�R���Ƃ����I�t�B�X�R���s���[�^�Ŏ���Ɩ������A������J�i���͂�����ƁA�Ƃ����ŁA�l������ɂo�b�����ȂǁA���̂܂����������j�A��w���ł̃J�[�X�g�ł͐}���و��Ƃ��������ŁA�قڏo���R�[�X����O��Ă����B
�������Ȃ����N�ɁA����ƌ�̊w�p���V�X�e���̐�삯�ŁA����Ƌߗׂ̎O�̑�w�Ƃ��l�b�g���[�N�Ō��Ƃ��A����Ƌ���Ƃ���݉���Ō��ԂƂ������b�����x�������B�܂����A�������\�N��ɑS���̑�w�}���ق��l�b�g���[�L���O����A�w��Z���^�[�i���݂̍������w�������j�ɑS�Ă̑�w�}���ق̏����Ə�����W��A�}���و��̎d�����o�b�Ȃ��Ő��藧���Ȃ��Ȃ�A�ȂǂƂ����u�����v���K���Ƃ͑z�������Ȃ������B
��Z�N��ɓ���A�o�b���g�߂ɂȂ��āA�}���و����u�Ő�[�Z�p��菭�����̓��̘J���v�ƂȂ�̂́A�����Ԑ�̘b�ł���B���̍��̐}���ق́A��w�E���̒��ł��u�ςȐl�v�̏W�܂�A�Ƃ����w���]���������B�����g�͐}���و��̎d���͂��ƍD������������A�����Ă�ꂽ���A�ĉ�s㱂̐��i�������������̂��A��N�ڂŎR�̏�̈�w�}���قɒǂ������A�Ȍ�Z�N�Ԃ��������I�Ȑg�ƂȂ�A�����A����ł������čD������Ȃ��Ƃ���ꂽ�B
�o�b�����Ȃ��������A�����J�v���ŃA�N�Z�X�|�C���g�ƌq���ŁA�I�����C�������Ȃǂ�����Ă��āA���\�A����̍Ő�[�̏������ɂ͂����̂ł���B
�d���̏�Œm�肦����w�I�Ȓm���́A�G�C�Y��C�F���l�̊w���Ȃǂ����A����́A�₪�āu�o�x���̌O��v�Ȃǂ̏���ɂ��𗧂悤�ɂȂ�A�L�x�ɂ��鎑���́A���ꂱ���I�b�N�X�t�H�[�h�p�ꎫ�T�i�n�d�c�j�͕��ʂ̕S�Ȏ��T�Ȃǂɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��V�F�C�N�X�s�A����̐l���^�Ƃ��Ă����p�\�ŁA��w�܂ŋ�肾�����p�ꂾ���A�����ڎ��T�̂�������A���ꂪ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B������Ǝ����������K�����Ȃ����������A�d���Ǝ��M�̕K�v����A���̂܂ɂ�����I�Ɏ����������l�Ԃւƕς���Ă������B���ł��p�a����э��ꎫ���͍��E�ɂ���A���ł��s���A�܂��͕s�ڂ̌��t�������K�����g�ɂ��Ă���B�ق��ɂ����m��w�Ɋւ����发�ȂǁA�ӂ��̐}���قɂ͂Ȃ��{���A���ɂƂ��Ă͒m���̕�ɂƂ��đ��݂����B�����ɋ߂Ă���̂�����A�g������ł���B
�܁A�i�D�悭�����A�����̎��͋t�����t��ɂƂ��ď����ɕς����̂��낤�B
�Ƃ͂����A���X�ɒ��҂��v�ɂȂ�̂��A�l�����̂��B�����ŁA����Ȍ�A���͏��Ǝ�`�Ƃ̐܂荇���������͍l���ɓ���i�Ƃɂ������\����Ȃ��̂ł́A�b�ɂȂ�Ȃ��̂Łj�A���������Z���V���[�Y���̂��\�z�����B�����āA�v�ɂȂ����������҂ŁA������̍ŏI�珑������i�̎�l���A�������E�g���c�L�[������ɂ����A����l���A���̍��������Ă�����w�r�e���̔N�Ⴂ�F�l�������l�����V�����u���I�̗c�N����Ƃ����ݒ����A�܂����̃������i�ƃI�����W���j�̓o��ҁu���s�s�v���A���O�N���珑���Ă������ƂɂȂ�B
���O�N�B���̍��A�����A�����ē�R�������F�����A�܂��O�\�ΑO�キ�炢�ŁA�����̉\��������ɐM���Ă����悤�Ɏv���B�ނ��A�Ȃ�̍������Ȃ��̂����A�N�����܂��Ⴍ�A�����͖����Ɠ��`�ŁA�ȂɂЂƂm���Ȃ��̂͂Ȃ��B�ی����Ȃ��~�����Ȃ��B�����A����^���Â̋P�₭�����������������B
�܂��A���̐l�͂Ƃ������A���ɂ́A�S���s�m��Ȗ����̑���ɁA�����ɂ́A�����̉\��������悤�Ɏv�����̂��B�r�e�E�Ŏ������Ȃɂ��Ȃ��邩�A���������ʂ܂܁A�����A���l�������Ȃ����̂������B���������̐��E��z���B�������ʔ�����A����ł����B���l�̕]����]�����ꂸ�ɏ����Ă������B�����������ӂ��������悤�Ɏv���B
���̏؍��Ƃ��āA���O�N�ɂ́A���͎��ɐ��͓I�Ɏ��M�����B
�u���s�s�v�������A�V���[�Y�Ƃ��āu�~�̏�v�u�������y�Ձv�ƃ���������l���Ƃ����i�������A�ˁA�u�����̐^���v�▢���ɏI������u�����o�[�̈�Y�v�Ȃǂ��������B���̍��ԂɁA���l������̊�e�˗��ɉ�����`�ŁA��R������ɂ́u�k���q�H�v�i�u���̗��v�����̃t�@���W���̕������ƒm�����̂��A���̍����j�ɁA��Ƀ}���K�ŕ`�����u���H�v�����������ď�������A�܂��A�F���́u�Ȋw���E�v�ɂ́A�u�e���̎��v�����߂���܂����������B�t�@���W���ւ̊�e������A�ނ�������A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悩�����B
���̈�N�ŁA���͈�Z�Z�Z���ȏ�A�����Ă���Ǝv�����A�����ł���ԁA���M�ʂ����������[���̈�N���������낤�B
���̐l����́A���̂ǂ����r�e�ȂA�Ɩ����قLj�E������i�ł��A�ꂸ�ɏ������B���ꂪ�₪�āu���V�g�v�Ƃ����A�r�e�I�v�f���܂����������ɂ��ւ�炸�A�����ł͂r�e���Ǝv���Ă��邵�A�r�e�̃��[�x������o�Ă��邩��A�Ȃ�ƂȂ��F���r�e���Ǝv�������Ȃ��A�Ƃ����������̍�i�ւƌ������Ă����B
�u���V�g�v�́A���Ԃ�A�u�o�x���̌O��v�ƕ���Ŏ��̑�\��ƌĂׂ�ނ��̂��̂��낤���A�����ɂ́A�F�E��R�������Ƃ̌�F����w�v�z��v���̂��������e����^���Ă���Ǝv���B����͔��l�N�Ă��甪�ܔN�Ăɂ����āA���N�Ԃŏ����グ���i��ɁA���Ȃ���M�����������Ă͂���j�B�V�g�ƃh���S����������z���Ēǂ���������������A�Ƃ����o�J�r�e�݂����ȃV�`���G�[�V�����́A�����g�����̏��N����i��������Ƃ������j�A�r�e�ɂ̂߂肱�ރL�b�J�P�ƂȂ����A�u�ʂ��Ȃ�����̉ʂɁv���������Ɓu�S���̒��Ɛ牭�̖�v�����������̓��ւ̃I�}�[�W���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����A���Ƃ��A���ꂾ���ł͂Ȃ��B�P�Ȃ�͕�Ȃ�A�킴�킴�����g���C�X�g�[���h����܂ł��Ȃ����炾�B���҂̔ᔻ�I�p�����A�Ə���ɉ��߂��Ă���B
���́A��̂ɂ����āA�ǂ̍�i�ł��A���̎��X�̎����̐g�̏�ɍ���Ȃ��A�������݂ւƔw�L�т���X���ɂ���̂����A���̍�i�ł��A����͔ۂ߂��A���Ȃ�w�L�т��ď����Ă���B���̓����A�����������Ă�����̂ł͑��肸�A�������������Ȃ����̂܂Ŋ܂߂āA����������𓊓����āA�悤�₭�������������̂ł���B
���̎��́A�܂�Ŏ��o���Ȃ������̂����A�Ȃɂ���A�F���l�����P�b�g�������e������Ƃ��Ăr�e�I�K�W�F�b�g���o�Ă��Ȃ���i�ł���B���܂��܁A�����v��l�Z�Z�N�������_�@�ƂȂ��āA�����O���[�u�������V�̐v�ő����邱�ƂɂȂ�����A���̍�i�����ǂ�h���Ȃ̂��A���̂܂ɂ���i������̃G�b�W�ɂȂ�K�^�����āA�������r�e�Ƃ��Ă��]�����ꂽ�B����͍ő�̋����ł���B
���āA������ł�����ٍ�u�Ԏ�l�v��]���āA�u�����}���K�̂悤���v�Ɛ�̂Ă��A�����A���̎��i�����]�ƁE�R��_�ꎁ�́A���̌�A����m�v�r�e�В��̎Ⴂ�l���犩�߂��āA�u�{���̏����}���K�v�����ۂɓǂ݁A���ɑ哇�|�q�ɂ͏Ռ����āA���̒��ҁu�ԂƋ@�B�ƃQ�V�^���g�v�����������A���̎R�쎁������A�u���V�g�v�͍����]���āA���́A�S���Ȃ����l�ɏ����}���K�����߂邱�Ƃ����_�ł͂Ȃ������Ɗ������������̂����A���̂͏�����Ƒ債�ĕς��Ȃ��̂ɁA���]���̂�����A�܂��͂������҂��ׂ����낤�B
���́A�ȑO�Ɂu�s���s�v�Ŏ��s�����A���z���݂Ɛl�ԂƂ̊ւ�荇�����A��ܑ���́u�n�����b�g�s�v�ł��łɕ`���Ă��邪�A�u���V�g�v�́A���̉�������ɂ���i���ہA�\�z�i�K�ł́A���̓�̍�i�͒ʒꂵ�A�����̊W�ɂ������j�B�����ł́A�l�ԓI���݂��ʂ����āu�~�ςɉ����鑶�݁v�Ȃ̂��A�Ƃ�������肪���邪�A����͍ŏ��Ɏ����ǂ����}���K�ł���u�|�[�̈ꑰ�v�u�g�[�}�̐S���v�����]�s�̃��C���e�[�}�ł�����B�[�I�ɂ����āA�u�g�[�}�v�͍��̋~�ς���艻���ꂽ��i�ł���A�u�|�[�v�͂��̋~�ς̑r������艻����Ă���B���܂���{�I�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�w�i�Ƃ��Ă̐��m�Љ��ɂ����̂ł͂Ȃ��A���̍����I�ȃN���X�`���j�e�B�̕������̂��̂��A��艻������������i���Ǝv���Ă���B
�����āA����Ɠ����ɁA���̎��́A�{�[���N���X�`�����ł���F�F�V�ƁA��ɃO�m�[�V�X�v�z�́i�����炭���{�ŗB��́j�ݖ쌤���ƂƂȂ��R���̗����̂��̂ł�����̂��B
�v���Ԃ��A�����ŏ��Ɏ�ɂ����r�e�t�@���W���u�Ȋw���E�v�A���̎l�ꍆ�A�l�ł���l���_������킵�Ă����u�r�e�ɂ����钴�z�T�O�ɂ��āv�Ƃ����_�l�ɁA����͒�������e�[�}�Ȃ̂ł���B�����ē�l�Ƃ��A���̎������Ȃ��A���������Ă�����B����͎������l�Ȃ̂��B
�����͈ڂ炸�Ƃ��]�����A��q�͘f�킸�Ƃ��]���B
�i���̎��́A���ՓI�ɕς��Ȃ��Ƃ��]���ׂ����낤���B
�����A���łɁA�|�X�g���_�������s�ƂȂ�A���̎�����郊�I�^�[���́u�傫�ȕ���̏I���v�Ƃ������������A���Ԃɂ͕����ɂ����z���Ă����B�����A���́A���ꂱ���u�傫�ȕ���v��`�������āA�r�e�������Ă����̂��B�����āA����͂�����x�A���̎����ɍR�����ƂɂȂ��Ă��A�Ȃ��������Ă����Ǝv���B���̔�����I�o�b�N�{�[�����e�Ȃ���x���Ă��ꂽ�̂��A����l�̎v�z�ł���v���������悤�Ɏv���B
�J�g���b�N�ł�����F���́A���łɎ���̍Ő�[�̎v�z�Ƃ��āA�|�X�g���_������A���̐�̃|�X�g�\����`��E�\�z�̐��E������ɓ���Ă������A�����������u�傫�ȕ���v�ɂ��A�������E�̃��^�t�B�N�V�������ɂ͕]����^���Ă��ꂽ�B�܂��A��R�����́A�����̒��z�T�O�̍l�@����A�O�m�[�V�X�v�z�̍l���ւƃV�t�g���Ă������A�����܂��A���Ă̕��������i�H�열�V��⑾�Ɏ��Ȃǁj�Ɠ����Ȃ݂ɁA������ǂ݂���ł��邪�A���ɐM�k�ɂ͂Ȃ�Ȃ������^�Ȃ�Ȃ������u���Ȃ��O���v�̐l�Ԃ�����A�N���X�`���j�e�B�ɂ́A����ȋ����������Č��Ă���B���̎��_���玁�̎d���ɂ͊S���������B
�N���X�`�����ł���ȏ�ɁA�䑸������q�̃L���X�g���w�̑דl�ł��������F�F�V���͂ނ��̂��ƁA�N���X�`�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ɁA���̕ӂ̃L���X�g���w�̋�������������ǂ݉����A�ْ[�Ƃ���Ă����O�m�[�V�X�v�z�ɂ������A�L������Œ��z�T�O��˂��߂Ă����R�����̎p���ɂ́A�������N���X�`�����ł��Ȃ��̂Ɂi�~�b�V�����Z�ɂ͒����ݐЂ������j�A������ǂ݂ӂ����Ă��鎄�͋����䂩�ꂽ���A�������������̂��B����͍��ł��ς��Ȃ��B
���Ƃ��A�W��ɏグ���ƕ��̉̈���A����ɂ͖����̃��g���b�N�Ƃ������A�Í��ɋ߂��u�V�сv���قǂ�����Ă���B����͉̂��������s�ŋL���A���̉̂̍�҂��Ɠ`�����Ă����C���A�����̐��E��s���钷���ő��������L���X�g���i�i���j�ɒ��z���āA���̐��_���̂ɓǂ݂��u��̎��i�C�G�X��Ȃ��Ď����j�v�������яオ��B���l�ɁA�W��̂����܍s�ŋL���A�����H�v�������яオ�邱�ƂɋC�Â����낤�B�V�тɂ͈Ⴂ�Ȃ����A����ɂƂ��ẮA�̂��҂��Ȃ�ʗV�тł���B�\�ʓI�Ȋ|�������Ȃ�A�ӂ��̌ÓT�̊w�K�ł����邪�A��d�O�d�ɔ邳�ꂽ���t�̗V�т́A�S�C������̂�������B
�����������A�����ɂ́A�����Ǝ�̂����w�I�Í�������B�C�X���G�����ŖS�ɕm�����o�r�����ߎ�����ɏ����ꂽ�u�G���~�A���́v�ɂ́A����͉̂Ɠ��l�́A�e�A�̓��������A���̂܂܃w�u���C��̃A���t�@�x�b�g�ɂȂ��Ă���A�Ƃ������u�V�сv������̂��B�������łт����Ă���A�܂��ɂ��̎��ɂ����A�����������|�I�ȗV�т��A���g���b�N����g���āA�ő�̕��|��i�ނ̂��A�܂�u�����v�Ƃ������̂ł��낤�B�i�`�X��̉��̃p���ŁA�u�V��V�~�̐l�X�v���B�����f��l�����Ɠ��l�A��i���̂��A���W�X�^���X�ɂȂ��Ă���̂ł���B
�����Ń��g���b�N�Ƃ́A�P�Ȃ錾�t�V�тł͂Ȃ��A�������m���̏ɂ��鎞�A�����炱���A�������g������i�������Â邱�Ƃ��A�łтւ̍ő�̒�R���肤��̂��B
���|��i�̒��ɈÍ��I�ȗV�т�����A�Ƃ����_�ł́A�Ñ�̉̂̐��_���A�r�e��~�X�e���͂ǂ̕���������I�Ɏ�����Ă���B
�����́A�ƕ��̖���ł���A��C�̖���ł���A�����Đ��_�I�ɁA�G���~�A���̖̂����m��ʍ�҂̖���Ȃ̂��B
���ꂱ��O�Z�N�ȏ�ɂȂ钷���t�����������A�N�Ɉ��͂r�e��ƃN���u�̏W�܂�ő����F���Ɋr�ׂāA�����𗣂�Ȃ���R�����Ƃ́A����܂ŎO���A���̓��A�����E�ł͉�������Ƃ��Ȃ��B�����A��Z�N�㏉���ɁA�������Ɋ��߂��o�b�ƃp�\�R���ʐM�i��ɂ́A�C���^�[�l�b�g�j�̐��E�ŁA�قڕ����I�����͖�肪�Ȃ��Ȃ����B�����������ɂ�������́A�钆�̒��d�b���������̂��A���܂�̋��ł��镟���ɋA���Ă��Ă���́A���[���ɕς�����B
��Z�N��Ȍ�A���̕\�ҋƂ̑�w�}���قł��}���ɓd�Z�����i�݁A�}���كV�X�e������������A�}���و��̎d������ς����B�f�[�^�x�[�X�̌����͐��E�̑�s�T�[�`���[�ł͂Ȃ��A���p�҂������ōD���Ȏ��ԂɍD���Ȃ��������ł���悤�ɂȂ����B����������A��s���Ă����̂́A�c�a���̂̍��z�������A�A�N�Z�X����ʐM���������z���������炾�B���ꂪ�C���^�[�l�b�g����ɂȂ�ƁA��w���c�a�̃A�O���Q�[�^�ƌ_�A���p�҂͖����ōD���Ȃc�a�𗘗p�ł���悤�ɂȂ����B�����G���W���Ɠ������o�ŁA���x�ŐM�����̍����w�p��A�����Ō����ł��A����ɂ́A���̂܂܃V�[�����X�ɓd�q�W���[�i�����{���ł�����������Ă���B
���Ĉꕪ�ԂȂ������ŎO�Z�Z�~������������n�c�a�́A����Ĉ�w�}���ق�PubMed�Ƃ��Ė����őS���E�Ɍ��J����Ă���B�����m�푈���A����̎��}�́A�܂�O�g�ł���uIndex Medicus�v��A�����E�����w����̂c�a�uBiological Abstracts�v��uChemical Abstracts�v�Ȃǂ́A�č������{�ւ̋֗A�[�u���Ƃ����B�Ζ��Ɠ��������ł���B�����́A����������ŁA�ǂ��������̕������ǂ̐�厏�̂ǂ��ɍڂ��Ă��邩�A�Ƃ�������������Ă��邾���Ȃ̂����A�����f�����ƁA�����҂͂Ƃ���ɍ�������B����Βm�̐��E�ł́u�헪�����v�Ƃ��ĐΖ��Ɠ������A�K�����ւ̋֗A�[�u���u����ꂽ�̂��B
���ꂪ���ł́A�i��w����s���Ďx�����Ă��邩��Ȃ̂����j�w���ɂ������A�����ł�����ł��g����B�������������݂̂Ȃ炸�A�ꎟ�����ł���d�q�W���[�i�������A�����̌������ɂ��Ȃ���ɂ��āA�A�N�Z�X�\�Ȃ̂��B�����̒̓R���O���}���b�g���肪���A�A�O���Q�[�^�ƌĂ��ނ�ւ̔N���Ή��͐��S���ɂ���Ԃ��A��ʗ��p�҂ɂ́A�����������̎���͔���Ȃ��B�m�̑㏞�́A���̎���ɂ������̂ł���B
�ȑO�A���ۂɌ����̌����҂ł��鐣���G�������u�u���C���E���@���[�v�ŁA�����������E�i�������̋��߂镶�����l�b�g����_�E�����[�h�����ʁj��`�������Ƃ����邪�A�ɂ��ނ炭�́A�ނ͂��̎��_�ł́u���݁v�ŁA���ꂪ�\���ƕ`���Ă��܂��������߂ɁA������������ᔻ�𗁂т��B�����҂ł͂��邪�A���ۂɕ��������Ȃǂ͂��Ȃ��������̂��A�旳�_�˂��������B�����A�ނ������A�������������́u���v�ɐݒ肵�Ă����A����͐��������݂ɂ́A�����\�Ȑ��E�ɂȂ��Ă���B�����̌���������A�ہA���O�C���F������A����ɂ��Ȃ���ɂ��āA�o�b�Ŋw�p�����������A�K�v�Ȏ�����d�q�W���[�i���Ƃ��ă_�E�����[�h���邱�Ƃ��\�Ȃ̂��B
�����������x���{��`�^���x��Љ�ɂ����āA�Ȃ��A���z�T�O�Ƃr�e�́A�܂��e�Ղɂ͗n�������ʊW�ɂ���B
����Ɂu�_�v�Ƃ̓����Ƃ����������ƁA������������R�c���I�珔�����ׂ����悤�ȁA�Ȓ��z�T�O�Ƃ��Ắu�_�v�Ƃ̓����A�Ƃ������}���ƂȂ��āA�����Ɏ����o�����J�[�h���A���܂��ăN���[�N�́u�c�N���̏I���v�ƂȂ�B
���́A��������A�N���[�N������̏o���ł����p�鍑�̋��A���n�ł���Z�C�������ƃX�������J�ɏZ��ł�����A�I�N�V�f���^���Ȗ��̑[��ɑR���邽�߂ɁA�I���G���^���Ȏv�z�������Ă����肷��̂́A�v�z�I�Ȕs�k��`���Ǝv���Ă����B
�N���X�`���j�e�B�Ƃ������N�ɂ킽�鋐��Ȏv�z��Ԃ��������H���j��̂́A����̃��U�ł��邪�A�����ɁA�S���̊O������I���G���g�v�z��R���_�Ƃ��Ď����Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��B�܌��v���Ȍ�̌���v�z�Ƃ������s�����悤�ɁA�����܂ł��I�N�V�f���^���Ȏv�z�ɓ��݂���T���j�]���l�����āA���m�������A�����ăN���X�`���j�e�B���������ꂩ��ے肷�邵���A�Ȃ��Ǝv���Ă���B
��R�����́A���{�ł��������A���������������������Ă�����l���B
���́A�����̎Ⴋ���ɁA������������ȍ˔\�Əo���������ƁA�����ɉe�������K�^����ɂ��肪�����Ǝv���Ă���B�I������Ɖ]����u�傫�ȕ���v�����A�������i�Ƃ��ĕ�݂��ނɂ́A����𗽉킷��قǑ傫�ȕ��C�~���K�v�����A���̕��C�~���Ō�ɂ͂܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A����ɂ́A�ʑ��I�ȃ|�X�g���_���v���Ō��ꂽ�悤�Ȑm���ł͖���������̂��B
���E��ς���ɂ́A�����Ɖ�����̓I�ȁu���q�v���K�v�ł͂Ȃ����B���邢�͒n�������A�V�����قǂ̎v�z�I�ȗ͓_�A��p�_��⏕���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���m������N���X�`���j�e�B���������������悤�ȁA�����ɂ͔����e�I�Ȏv�z���K�v�Ȃ̂����A����́A�D�L���A��\���I�Ŕ���c���āA��\�ꐢ�I�œX���炵�ɂ����Ă���悤�ȁA�����I�Ȏv�z�������A�������������́A�N���X�`���j�e�B���N���X�`���j�e�B�Ƃ��Đ������A�������������Ɉْ[�ł������O�m�[�V�X�v�z�ȂǂɁA�݂�悤�ȋC������̂ł���B
���̂悤�ȍl�@�ɁA��R�����̋����͑����̎��������ɗ^���Ă��ꂽ�B
�܂��A�{�i�I�ɁA���́u�G�v�������Ă͂��Ȃ��B�܂�������Ă��Ȃ���i�ŁA������Ȃ��ɂ́A��͂�A���������Ñ�̉b�q���K�v�Ȃ̂����m��Ȃ��B���̎x�������Ă����A���́A�����n�߂��G�N���`���[���ɂ�����ǓƂȓ�����S���ł���̂����m��Ȃ��B
���\�N��ɒm�荇������̑傫�Ȓm�I��F���A���������x���Ă���Ă���B
���́A���̋��R�Ƃ��K�^�Ƃ������ׂ����荇�킹�Ɋ��ӂ��Ă���B
���A���͊җ���}���A�݂��ɔN���Ƃ����B
�����A�̗͓I�ɂ��C�͓I�ɂ��A�傫�Ȏd�����o����Ō�̒i�K�A�l���ɂ�����A�V���̎����ɍ����������Ă���B
���\�N���A�t�̂������ɂ�����X�́A�݂��ɁA���̂悤�ȓ��X�������ɖK���ƒN���\���ł������낤���B
�V���ȂǁA�����ɂ͖����̂��́B���邢�́A����܂łɁA�������Ƃ������Ă��܂������m��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A�������V�c��V�X�����炷�Ƃ́A�N���l���Ă��Ȃ������B
�����A����ɂ��A�����ĕ����ɍΌ��͒N�ɂ��K��A�������V����̂��B
�����Ɏl�Z���N���}����u�k���q�H�v�����͌c�ꂷ����̂����A�����āA���̎�Ɏ҂����R���������j�����̂ł��邪�A�������A�����ŏI����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ɂ͂܂������B
�����ɂ́A�܂��A�o��������̐t�̓��X�ɐS�ɒ�߂��ʂ����ׂ��������A���܂����������Ă��Ȃ��A�����������ꂼ��̎v��������͂����B
���̎����A�j��T�C�N���ł���A�܁Z���N�܂łɁA���ꂪ�ʂ����邩�ǂ����A����Ȃ����A���݂��A�����c���ꂽ���Ԃ͏��Ȃ��B
�����đn��Ƃ͌ǓƂȉc�ׂɑ��Ȃ�Ȃ��B�ʌɓ����A�Ƃ��Ɍ��B
������������I�ȏ�A�݂��Ɂu��F�v�Ƃ��āA�ǓƂɂ��ꂼ��̓����������Ȃ����낤�B
�V���Ȃ�u�ʂ��Ȃ�����̉ʁv���A���邢�́A�V���Ȃ�u�S���̒��Ɛ牭�̖�v��ڎw���āA���̋��E��˔j���Ƃ��A�Ƃ��ɋF�����ł���B
�������̌���̂悤�ɁA���邢�͓~�̍ŏ��̐�̂ЂƂЂ�̌����̂悤�ɁA�~�肵����₽���m�̌[�����A���ꂪ���łɘV���ɐI�܂�͂��߂������ɁA�Ō�̗��z�������炷�F����F���āA���͂����A����������Ƃ��ɕ��O�l�̑��ǂ���A�S����j������B
���Ȃ��̌��݂Ɖߋ��Ɩ����ɁA�K���ꂩ���B